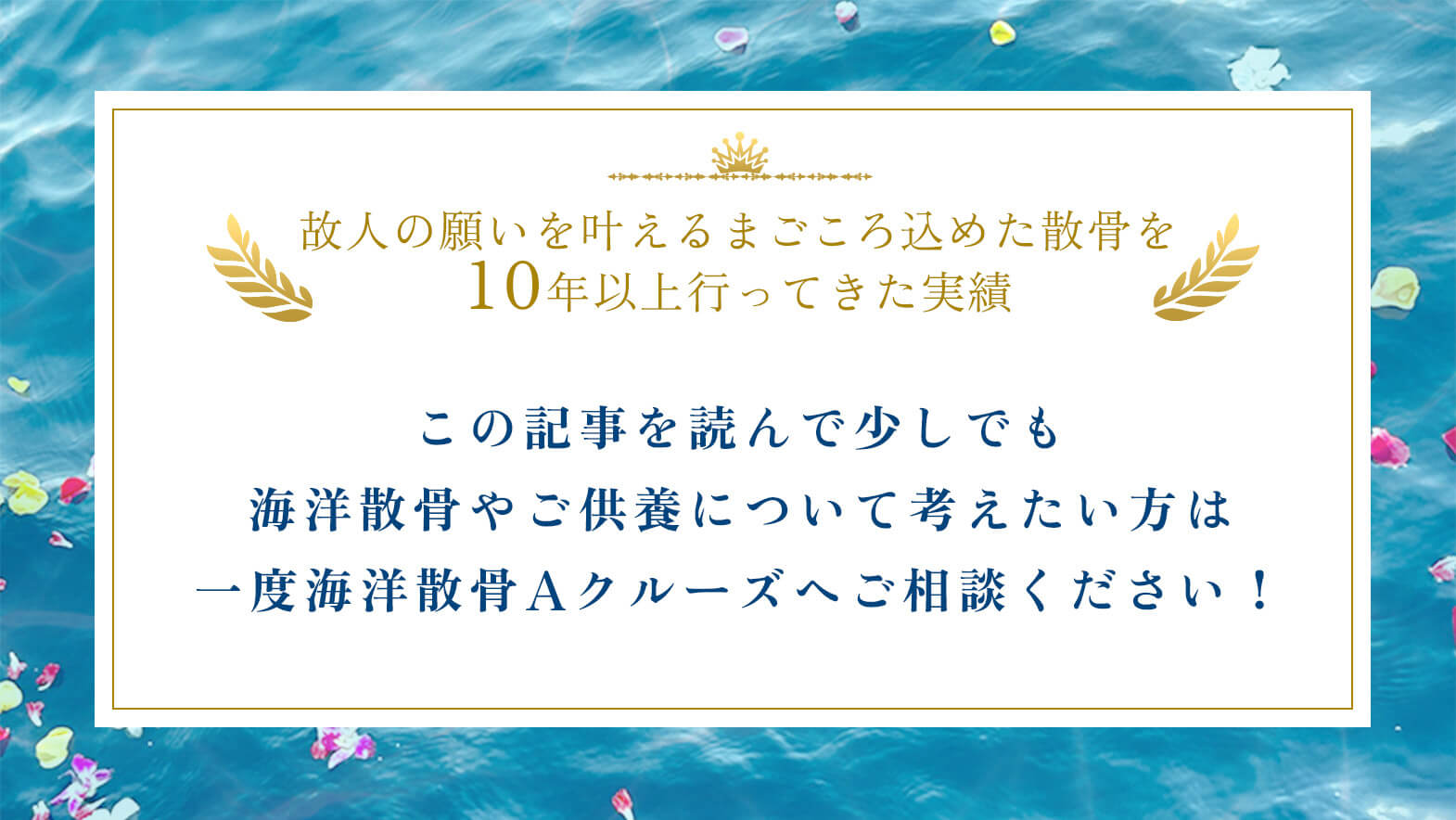無縁墓の増加という問題は、日本中で年々深刻化しています。
その原因には、少子高齢化・核家族化が影響していると言えるでしょう。
無縁墓はお墓が放置された状態であり、いずれは多くの人に迷惑をかけて撤去されることになるのです。
今回の記事では、お墓が無縁墓になる理由や今実施するべき効果的な対策についてまとめました。
家族のお墓を無縁墓にしたくないと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
無縁墓とは何か
無縁墓とは、お墓を承継する方がいなくなりお墓が放置されている・管理料も支払われていない状態を指します。
お墓は墓地に定められた費用を支払うことで適切に管理されますが、お墓の使用者・承継者がいないまたは不明な状態が続くと、無縁墓になってしまうのです。
無縁墓は墓地の管理者に大きな負担をかけるだけでなく墓地を占有し続けることから、管理費を一定期間滞納したお墓は撤去されるケースが多いです。
無縁墓の条件
無縁墓と認められる条件には、お墓の継承者がいない/不明であることと、施設が設定した期間を過ぎても管理料が支払われないことの2点があります。
管理料の上限滞納期間は施設によって異なりますが、3年から5年が設定されています。
しかし、お墓の解体や撤去にも費用がかかることから、無縁墓は墓地の存続に関わる問題だと考えるべきでしょう。
無縁墓を処理する手順

無縁墓にはお墓の承継者がいないものの、墓地の管理者が自由にお墓を撤去することはできません。
ここでは、無縁墓を処理する際の流れについて説明します。
墓地整理告示をする
霊園や寺院では、法律で定められた手続きに則って無縁墓を処理します。
まずはお墓が無縁墓であると判断するために、管理者が見つからないお墓について官報に記載した上で墓地に立札を1年以上立てて公示します。
一定期間公示をしてもお墓の管理者が現れない場合には、お墓が無縁墓であるとみなされるのです。
墓石の撤去
墓地整理告示をしてもお墓の管理者が見つからない場合は、墓石を撤去することになります。
実際の墓石の撤去作業は、石材店などが実施します。
この際にかかる費用がお墓の相続人に請求できなかった場合、墓地の管理者または自治体の負担になってしまうでしょう。
お墓が撤去されて更地になれば、新しいお墓を建てられる状態になります。
合葬をする
無縁墓から取り出された遺骨は合同墓などに合祀されます。
合同墓では複数の遺骨を合わせて扱うことから、一度合祀された遺骨は取り出せません。
お墓が無縁墓になってしまう原因
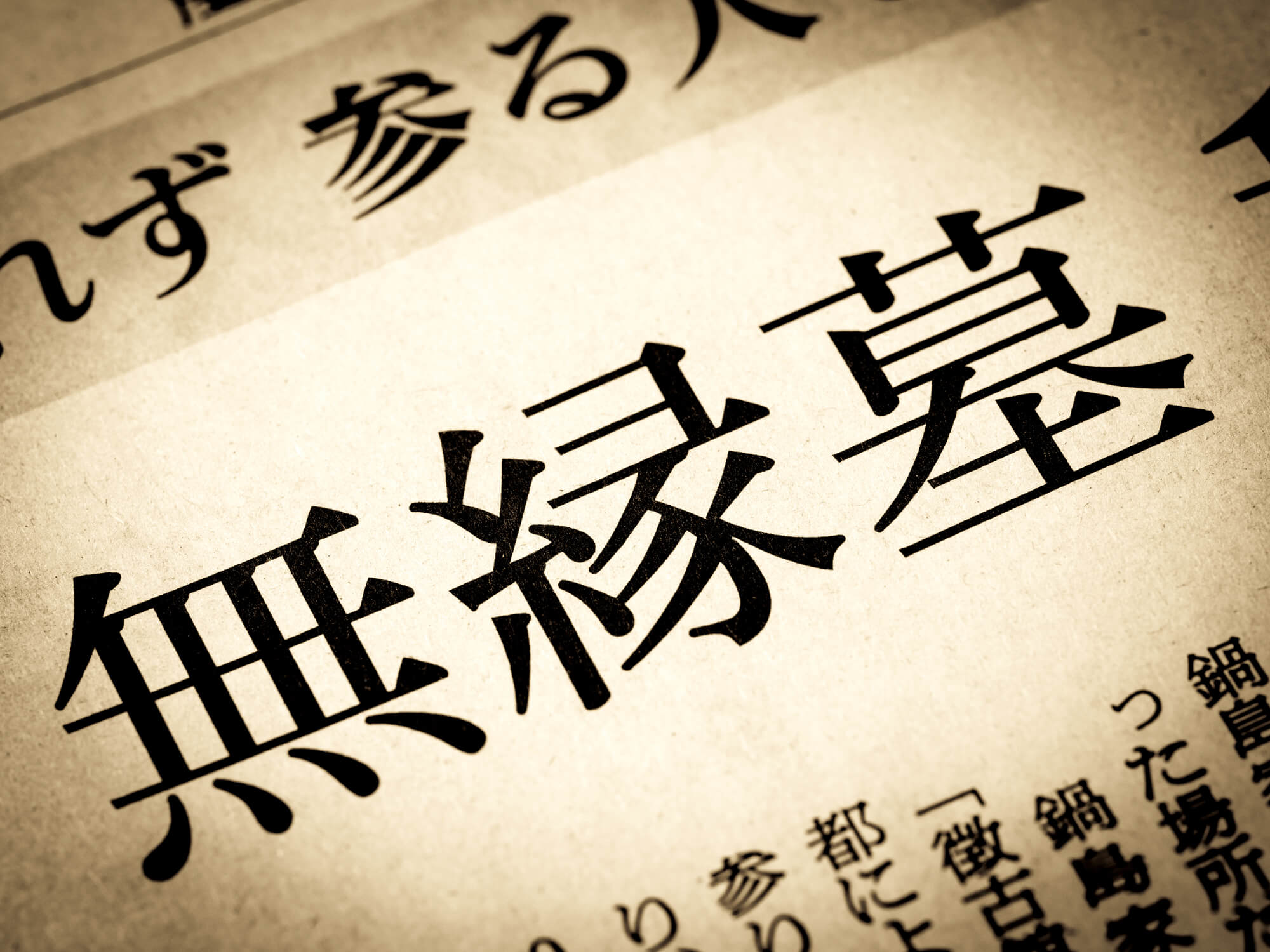
現在日本では無縁墓が年々増加しており、墓地のみでなく地域全体の負担になっています。
無縁墓の処理にかかる費用を自治体が支払う場合は、地域の住民が税金として負担を負うことになるでしょう。
現段階ではお墓の承継者がいるからと言って、無縁墓は決して他人事ではない事実を知っておいてください。
少子高齢化により後継者がいなくなる
社会的に深刻化している少子高齢化問題の影響を受けて、お墓を管理する後継者がいなくなり、無縁墓が生まれるケースは多いです。
年々減少を続ける出生率を見れば、将来的にお墓を維持することは難しいと言えるでしょう。
継承者がいない状態では、お墓を管理する・管理料を支払い続けることができません。
核家族化が定着した
お墓がある生まれ育った土地で生活を続けるのではなく、都会で仕事を見つけ核家族で暮らすスタイルが定着した現在では、お墓の管理が難しいと感じる家庭が増えています。
お墓掃除を含む管理のために何時間もかけて地元に帰るというのは、現実的とは言えないでしょう。
お墓をお引越しするという手もありますが、このような状態が放置されて無縁墓になってしまうケースも少なくありません。
お墓に対する価値観の変化
「家を継ぐ」「お墓を守る」という価値観が薄れている現代は、お墓に関する文化の継続が難しくなっています。
時代の変化に合わせて、お墓に対する価値観も別のものに変わってきたと考えるべきでしょう。
お墓を無縁墓にしないための方法とは

お墓を、無縁墓にしないためには、次のような手段があります。
自分の代や子供の代だけでなく、孫以降の代のことも考えて必要な準備をしておきましょう。
永代供養を考える
永代供養では、墓じまいをして寺院や霊園に一定期間遺骨の安置を依頼します。
定められた期間が経過した後は、合葬により遺骨を供養することになります。
必要な費用は契約時に支払いを済ませるため、無縁墓になる・子供や子孫に負担をかける心配がない供養の方法だと言えるでしょう。
永代供養の方法にはいくつかの種類があります。
お墓のお引越しを考える
現段階でお墓と自宅の距離が離れているのなら、お墓のお引越しをして自宅の近くに移動させるという手段もあります。
自分の代のお墓の管理の手間は少なくできますが、子供や孫が同じ土地に暮らし続けるとは限りません。
長い目で考えると、永代供養の方が現実的な選択肢であると言えるでしょう。
永代供養に踏み切れないという方や親族の了承が得られなかった場合には、お墓のお引越しを選び現段階のお墓の管理にかかる手間を減らすのも良いです。
永代供養の種類

お墓の管理を霊園や寺院に任せる永代供養には、次のような種類があります。
個人型の永代供養
個人型の永代供養では、用意された墓標に個別で納骨をして供養を継続します。
墓標は一般的なお墓以外に、納骨堂型としてロッカー式・仏壇式などから選択可能です。
定められた期間が経過した後は、墓標から遺骨を取り出し、他の遺骨と一緒に合祀されるケースが多いです。
合祀型の永代供養
個別型ではなく最初から複数人の遺骨を1箇所で供養する合祀型を選択することも可能です。
個別型と比較して必要なコストを抑えられますが、一度合祀した遺骨は取り出せません。
合祀型の墓標には、供養塔・観音像・記念碑などが用いられます。
樹木葬
樹木葬とは、墓標の代わりに樹木をシンボルとして用いるお墓のことです。
個別型・合祀型の他に、遺骨を混ぜずに遺骨を埋葬する集合型も存在します。
他の永代供養と同じように、契約期間終了後は合葬になるケースが多いでしょう。
散骨による永代供養

現在注目されている永代供養の方法に散骨があります。
散骨では遺骨を粉状に粉砕した上で、海や林などに撒いて供養をするのです。
「死後は自然に還りたい」と考えている方におすすめの永代供養の方法であり、子供や孫にお墓の管理の負担がかかる心配もなくなります。
散骨の種類
代表的な散骨の方法は、以下を参考にしてください。
- 海洋散骨:専用の船で海洋に出て遺骨を散骨する
- 山林散骨:散骨の許可が出ている山林で散骨をする
- 空中散骨:小型のプロペラ機などに乗って空中で散骨をする
- 宇宙葬:遺骨をロケットやバルーンに乗せて宇宙に飛ばして散骨する
多くの場合は、自分や故人の趣味・希望に合わせて散骨方法を選択します。
散骨にかかる費用の相場
散骨にかかる費用の相場は、海洋散骨・山林散骨で5万円〜、空中散骨や宇宙層では100万円近くの費用がかかるケースもあります。
永代供養に必要なコストを考えると、非常に手頃な価格であると言えるでしょう。
もちろん散骨後に費用が発生することはないため、一度きりの支払いで全ての手順を完了できます。
散骨と手元供養を組み合わせるという手もある
散骨で全ての遺骨を手放すことに抵抗がある方は、遺骨の一部を手元に残す手元供養と散骨を組み合わせると良いでしょう。
現在では手元供養の方法も多様化しており、遺骨を使ったアクセサリーを作ったり、おしゃれなミニ骨壷に入れたりして供養を続けられます。
手元供養を活用すれば、常に故人が近くにいるような感覚を得られるでしょう。
まとめ
管理者がいなくなり管理料の支払いもない状態のお墓を無縁墓と呼びます。
墓地の管理者は適切な手順を踏むことで無縁墓を撤去できますが、撤去費用や手続きは墓地のみでなく地方の自治体の負担になる可能性があるでしょう。
自分の代では問題ないと考えているお墓の管理は、次の代・次の次の代まで考えた対応が必要だということです。
少子高齢化が進んでいる現在では、自分たちのお墓を無縁墓にしないためにも、適切なタイミングでの永代供養を検討するべきです。
永代供養の方法には個別型・合葬型の他に散骨や手元供養があります。
家族に最適な供養の方法について、将来の見通しを立てた上で話し合ってみてください。